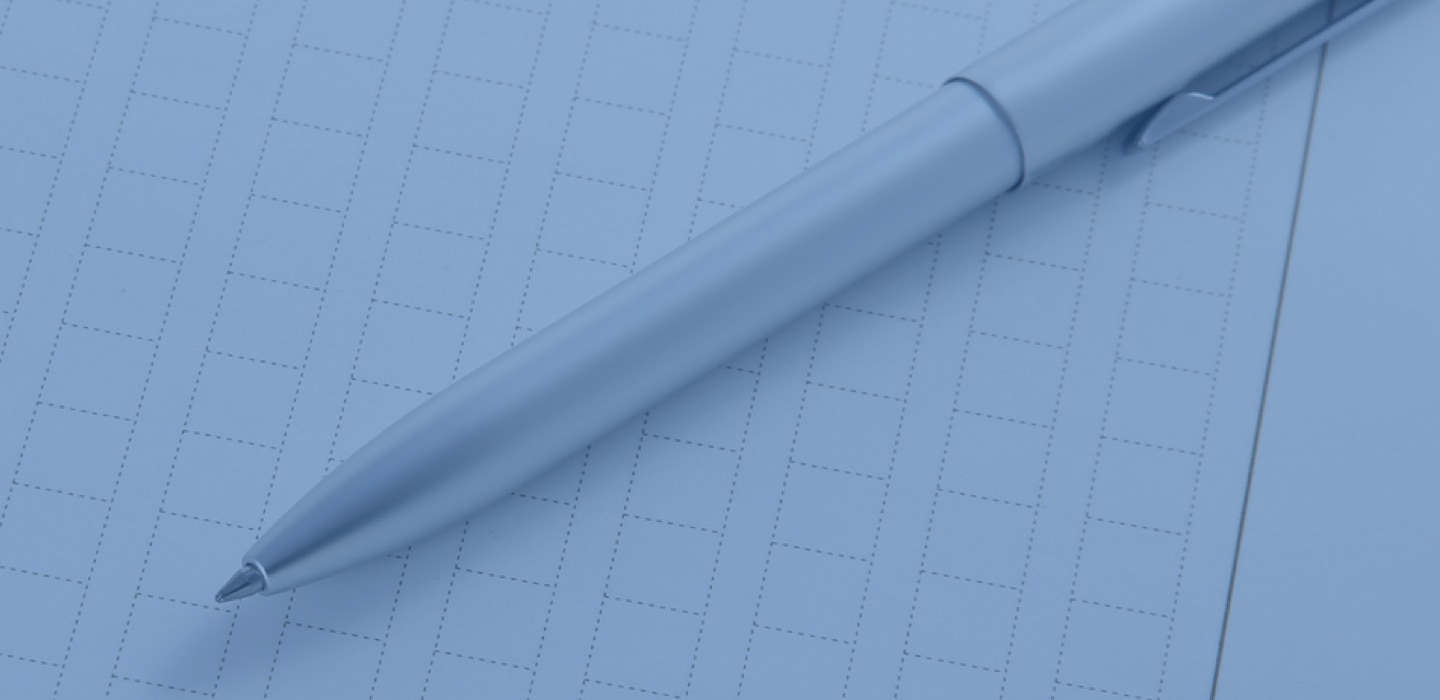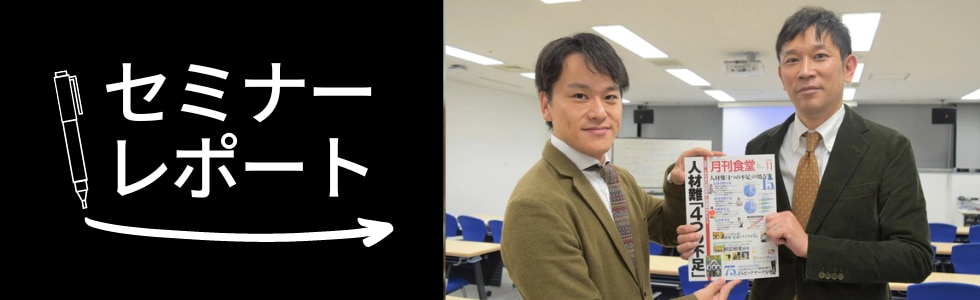
月刊食堂編集長が語る外食経営の最新潮流! 行き過ぎたデフレに苦しむ業界において、いま経営者が向き合うべきこと
1961年8月創刊、外食産業専門のビジネス誌として日本最古の歴史を誇る「月刊食堂」。食堂業がまだ“水商売”と呼ばれていた時代に「業界の近代化に貢献する」ことを旗印に創刊し、以降ビジネスに役立つ最新の経営情報を“外食記者”の視点で収集・発信し続けている同誌が2019年10月号に選んだテーマが、“人材難 「4つの不足」”。外食業界のみならず、日本のサービス産業全体の悩みである本テーマについて、同誌編集長 通山 茂之氏に、当社の外食統括コンサルタント 相崎との対談形式にてご講演いただいた。
※月刊食堂 編集長 通山 茂之氏(写真右)と、弊社MS&Consulting 外食統括コンサルタント 相崎 哲史(写真左)
※この記事は、2019年10月29日開催【月刊食堂編集長、外食経営の最新潮流を語る!】の講演内容をレポートするものです。
※記載されている会社概要や肩書き、数値や固有名詞などは講演当時のものです。
行き過ぎた外食デフレへの警鐘
通山氏:本日、皆さんにお話ししたいことは極めてシンプルで、「日本の外食価格って、ちょっと安すぎるよね」ということです。
今はもう閉店してしまったのですが、自宅の最寄り駅の駅前にカフェがありまして、そこで毎朝ロイヤルミルクティーを頼み、そのまま午前中少し仕事をしてから会社に行くというルーティンが私にはありました。毎日通っていると、段々と従業員の皆さんも自分の顔を覚えてくれるようになりました。こちらからわざわざ注文しなくても、「Mサイズですか?Lサイズですか?」の問いに答えるだけで、ロイヤルミルクティーが出てきます。しかも、いつもお願いしているテイクアウトカップに入って。また、それを持って会社に向かおうとすると、「今日もお仕事がんばってください」や「お気を付けて行ってらっしゃいませ」などの声をかけてくれるようにもなりました。
では、このサービスが、一体いくらで行われているのか。たとえば、コーヒーが1杯220円として、人件費率を多めに見て30%で計算したとしても、66円です。私は、このような高品質なサービスが、たった66円で提供されていること自体に違和感を覚えるわけです。諸外国の飲食店の取材をしていても、やはり日本の外食産業の価格設定はどう考えてもおかしいと感じています。お隣の韓国でも、某有名コーヒーショップの価格は、日本より100円くらい高く設定されています。これから日本の人口がどんどん減っていき、BRICsのような国々の経済成長が著しくなってくると、原価率がこの先下がる見込みというのは、ほぼないと思っていいわけです。そのような中で、日本国としてのバイイングパワーも下がっていったときに、今の価格のまま外食業界が進んでいくことは、構造的に無理があります。

私は、消費者にとって「安さ」というものは欲望だと考えています。しかも、強欲に近い欲望です。これまでの業界の取り組みを批判するわけではないですが、この欲望に際限なく応え続けてしまった結果、外食のいわゆる相場感というものが崩れてしまい、そこにあるべき労働対価が支払われなくなってしまったのです。
「値上げ」をして、叩かれてしまった企業さんもありました。価格を元に戻さなければ集客はできない、などの話になっていたりもしますが、私としては、そもそもこれを「値上げ」と言っていること自体に違和感を覚えます。「値上げ」ではなく、それは“従業員の方々の労働対価を適正値に近づけるための第一歩”だと考えています。ですので、月刊食堂誌上でも、なるべく「値上げ」という言葉は用いないようにしています。
併せて思うのが、外食商品はいわゆる付加価値商品である、ということです。機能が求められているわけではないのです。スーパーマーケットでミネラルウォーターが1本100円で売られているとします。それが400円や500円の価格で売れるかというと、絶対に売れません。ところが、たとえば雰囲気の良いバーで、そのミネラルウォーターがバカラのグラスに注がれて提供されたとします。すると、途端にその1杯に600円や700円が支払われるわけです。

本来、このような“シーンで丸ごと売る”といったある種トリッキーな価値の付け方というのが外食産業の強みであるにも関わらず、そうしないというのは少しもったいないと思っています。大手チェーンが機能店で、“安い価格で、クイックに、安定したサービスを提供する”ことが価値だとしたら、小規模事業者としては“付加価値創造”で勝負すべきなのです。
たとえば、綺麗に盛り付けて“SNS映え”させて、それを付加価値として価格に反映させるという手段が用いられていたりします。SNS代、いわば“映え代”です。十数年前にラーメンブームがあったときに、“情報食い”という言葉が流行りました。つまり、ラーメンそのものを食べに行っているのではなく、「そのラーメンを食べたよ」という情報を食べに行くというラーメンフリークの方たちがいたわけです。これが現代ではSNSに置き換わっているだけだと思っています。
また、経済学上でフレーミング効果と呼ばれる心理作用をうまく利用した商品もあったりします。たとえば、ポテトサラダの見た目をモンブラン状にして、スイーツ商品の枠組み(フレーム)で提供しているお店があります。スイーツには、実は原価積み上げ式、コスト志向型で売価を設定しているものは少なく、比較的高く価格設定ができる商材の一つと捉えています。ポテトサラダの見た目を替えて、スイーツのフレームで売価を設定するというのも、外食ならではの戦略だと思っています。
相崎:“映え代”やフレーミング効果をうまく取り入れた価格設定があるからこそ、戦略的に顧客が不満に思わずに単価が上げられ、利益を確保しやすく、結果として社員への還元もしやすい・採用もしやすい、という連鎖ができますよね。
通山氏:そうですね。もう一つは、価格を上げる根拠をどこに持つかも重要だと考えています。価格を上げる根拠が、外食産業に従事する方々にきちんと給料を支払うためである、ということが大事なのではないでしょうか。商品の価格を高く設定するのは、トップのやるべき仕事であると同時に、そのトップが従業員をどう思っているかの試金石にもなるのです。価格を上げるのは勇気がいりますし、実際に消費者の共感は得にくいかもしれない。それでも、そこに従事する方々に適正な労働分配をしていくという意識を持てるかどうかで、価格の付け方やどのように商品価値を出していくかということが、変わるのではないかと思っています。
単品FL管理でキッチンの生産性を見直せ
通山氏:単品FLについても触れておきたいです。仕込みの秒数とスタンバイの秒数、そしてオーダーが入ってからの調理時間を算出して、単品あたりにかかっている原価と人件費の合計を考える、という理屈になっているのですが、生産性を上げるうえで非常に良い仕組みだと思っています。
ある居酒屋チェーンでは、単品FLが50%となるようにすべての商品を作っていました。その目的は、商品のクオリティを一定にするためです。原価が高い商品は、元の品質が高いため、そこには手間はかけません。逆に、原価が安い商品には、ある程度の手間をかけないと商品価値が担保できない。それらをコントロールするための指標が、単品FL 50%だったのです。
この手法が優れているのは、そもそも仕込みやスタンバイの秒数を把握するにあたり、「誰を基準にするのか」という視点が生まれることです。要は、ロールモデルとなる社員を設定しなければならないのです。作業が早い人もいれば遅い人もいて、それぞれ手順も異なる。これを整えていく必要があります。本来、調理時間や作業手順が異なるのに、時給が同じという状況があまりよろしくない中で、“ロールモデル社員”を設定するということ自体が、外食にとって重要なのです。
相崎:その“ロールモデル社員”には、優秀な人を設定するということでしょうか。

通山氏:“普通にできる人より、もう少しできる人”を設定するといいかもしれません。多少下振れしても、それが普通の範囲に収まればいいと思っています。
単品FLを把握することで、キッチンのポジション毎の労働量と生産性が見えるのもメリットです。1日の全商品の出数も出ているので、単品FLと組み合わせると1日あたりの労働量、生産性の見える化が図れます。それに応じて、たとえばメニュー組みを見直すことにも繋がります。
労働量や生産性を把握することは、人材確保のうえでも重要です。人の問題を考えるとき、まずは理念共有やモチベーションをどう与えるかなどの軸で動きがちですが、個人的にはそれよりも先に離反要因を減らすべきだと感じています。モチベーションは、高い人と低い人とが出てきます。その状態を放置すると、生産性が高い人からやめていってしまう。会社として求める生産性、スキルや“店長像”などといったものを明示しないと、その職場にはずっと不公平感が蔓延してしまうのです。モチベーションはもちろん大事ですが、その前に企業として基本的なことをやるべきだと考えます。
外食産業における「店長」の評価制度について
相崎:月刊食堂11月号では、クレドについて触れていますよね。今回、そこに焦点を当てた理由を教えてください。
通山氏:クレドとルールブックという特集を組む予定なのですが、意識統一と判断基準というのが組織の大前提として大事だと思っています。
組織の根本において、どのような意思統一をするのか、つまり、みんなをできる限り一方向に向かわせるような取り組みと同時に、現場のスタッフが、いざ問題が起こったときや対応に困ったときに、それぞれ何を基準に判断すべきかを決められるようになることが重要です。それをマニュアルで縛るのではなくて、本人たちの自主性と意思決定に基づいて、店や企業が全体的に前を向ける仕組みを作った方が良いということに、今回の特集では触れています。

相崎:クレドやスタンダードは、いわゆる一般論になりがちだと感じることも多いのですが、自社の戦略に合わせて作るべきなのではないでしょうか。
通山氏:まさにその通りだと思います。本日触れたかった「店長の評価」についても、根本は同じです。会社が何を目指していて、どのような理想を実現しようとしているのか、ということが重要なのです。
どの企業も、店長に対する評価項目が多すぎる印象があります。利益を生む拠点の長でもあるわけなので、そこに多くを求めたくなるのは企業のトップとして当たり前ですが、逆に、店舗の運営において何を重視すべきかがフォーカスできていないことの現れでもあるのです。店長評価もKPI管理も同じです。何を評価すべきかの絞り込みが肝要です。
結局、企業はトップ次第というところがあります。トップがどのように社会貢献しようとしているのか、何を事業の目的としているのか、などを毎日自分に問い詰めていないと、段々とぶれてしまいます。お客様にどういう価値を提供したいのか、そのために店長に何を求めるのか、そして、それを実行するために何が必要なのか、を見失うと、おかしなことが起きてしまう。「店長」評価に関していうと、そういう問題が見えている。
現場の店長には、“本部アレルギー”の方が非常に多いです。店長にとって、エリアマネージャーやSVが自らの上司にあたるものの、その上司は常に自分の仕事ぶりを見ているわけではなく、二者の間には心理的かつ物理的な距離が生じ、結果、意思の疎通が難しくなるのです。たまにしか店舗を訪れないエリアマネージャーやSVが、ただただ文句だけ言って帰っていくと、店長もなかなか腑に落ちません。
たとえば、「固定客をどれぐらい取れたか」が評価項目にないのが不満、という店長さんもいました。要は、店長が評価されたいことと、本部が評価することとの間に乖離があるのです。店長評価のうち20%がお客様アンケートによって決まる、という企業もありました。これが、意外と納得感があったりします。取材した店長40名のうち、8割である32名がこの評価制度を好意的に捉えていました。店長評価を考えるうえで、このような視点も大切ではないでしょうか。
相崎:これが一般論として正しい評価項目というものは存在せず、①自社の戦略から絞り込む ②現場の納得感を生み出す 制度にすることが大切、ということですね。本日は多岐に渡るテーマの講演、ありがとうございました。